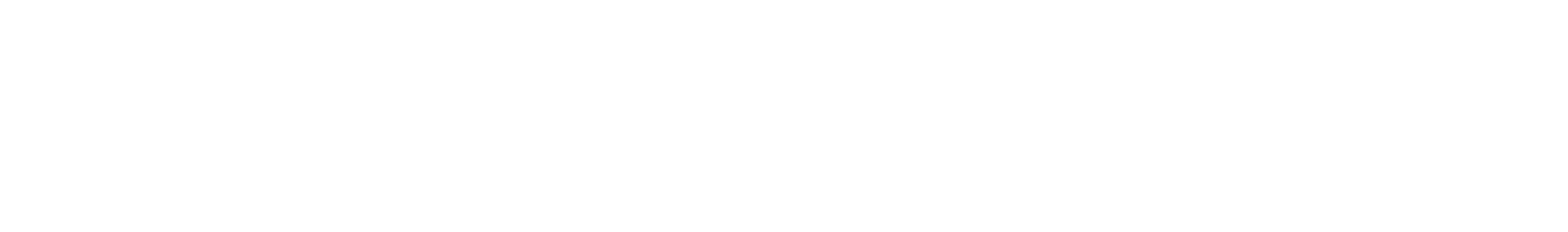紙カルテから電子カルテに移行する際の注意点
はじめに
近年、医療現場では電子カルテの導入が加速しており、厚生労働省の医療施設調査(2023年10月時点)では、普及率が55%を突破しました。
しかし、依然として紙カルテを使用している医療機関もあります。政府は2030年までにすべての医療機関で電子カルテの導入を目指す方針を掲げており、今後さらに普及が進むと考えられます。
私自身、勤務していた病院やクリニックで紙カルテから電子カルテへの移行を経験しましたが、その過程ではさまざまな失敗例も見てきました。
本記事では、電子カルテ導入時に注意すべきポイントについて解説します。
参考資料
自由民主党政務調査会『医療DX令和ビジョン2030』
厚生労働省『医療DXの更なる推進について』
2. 電子カルテ導入のメリット
① 診療時間の短縮と稼働率の向上
手書きのカルテでは、書く事も読む事も時間がかかります。
特に、医師の筆跡が判読しづらいことがあり(医師の皆さんすみません)、看護師や他のスタッフが情報を読み取るのに苦労する場面も・・・
また、過去の診療履歴を追うのも大変で、通院・入院期間が長い、症状が重症化している患者ほど情報収集の負担が増します。
② 情報共有の向上
電子カルテを導入することで、医師・看護師・受付スタッフ間の連携がスムーズになりますが、さらに、他の医療機関とのデータ共有も容易になり、紹介状の手書き作成や検査データのコピーといった手間を削減できます。
③ 紙カルテの保管負担の軽減
診療録は5年間の保管が義務付けられていますが、紙カルテの場合はその管理が大きな負担となります。保管場所の確保が必要であり、クリニックに保管スペースがない場合、保管するスペースの確保に別途コストが発生する場合もあります。
また、万が一数年前の患者情報が必要な場合に、情報を探す際にも時間と手間がかかります。
紙カルテから電子カルテへの移行失敗例
あるクリニックで、スタッフ主導で電子カルテを導入したものの、失敗してしまったというケースを見ました。
導入に失敗した原因
・自費診療を行っているにもかかわらず、保険診療向けの電子カルテを選定してしまった。
・マーケティング機能(自動メール送信、売上分析、売上見込み管理など)が搭載されておらず、それらを手動で行うことになり人件費が増えた。
・結果として、一度導入した電子カルテを別の電子カルテに切り替える必要が生じ、余計なコストと手間が発生した。
電子カルテ導入を成功させるためのポイント
① 現状の課題を洗い出す
まず、自院の課題を明確にし、必要な機能と不要な機能を整理することが大切です。スタッフにヒアリングしたり、自分で考えて何が問題なのか正しく理解すること。
・紙カルテの管理負担を減らしたい
・スタッフの業務負担を軽減したい
・マーケティング機能(リマインドメール、売上分析など)が欲しい
これらの要件を明確にした上で、電子カルテの導入によるメリット・デメリット、そしてリスクへの対策を検討していきます。
導入すること自体が目的になってしまい、運用を始めてから『こんなはずではなかった』とならないように注意が必要です。
② 複数の業者や使用者に話を聞く
電子カルテ業者は、自社の製品を導入してもらうためにメリットを強調しがちです。そのため、複数の業者と比較し、以下の点をチェックしましょう。
・診療科目に適した機能があるか?(皮膚科、内科、形成外科・美容外科など)
・操作が簡単でスタッフが使いやすいか?(医療従事者の中にはパソコンが苦手な方もいるため、教育体制も必要)
・コストとサポート体制は適切か?(導入後のアフターサービスがお金がかかる、またはサービスがないなど)
・ネット環境やパソコンの要件を満たしているか?
他にも実際に電子カルテを使用している医師の意見を聞くことも大切ですが、クリニックの運営形態が異なる場合は参考にならないこともあるため注意が必要です。
また、『導入が多いから』『他の医師に勧められたから』と安易に決めるのではなく、自院にとって本当に必要かを見極めることが重要です。
まとめ:慎重な選定が重要
一度導入した電子カルテを別のものに切り替えるのは本当に大変です。
数年は同じカルテを使用し続ける事になるかも・・・
初期段階で慎重に選定し、自院に最適なシステムを導入することが重要です。
「とりあえず導入してみよう」ではなく、事前のリサーチと十分な検討を行い、適切な電子カルテを選びましょう。
看護師・MBA(経営学修士)
クリニックの運営支援(経営・マーケティング・人事マネジメント)、保険診療クリニックへの自費診療導入、電子カルテやシステム導入まで幅広く対応。単なる助言ではなく、現場にあわせて伴走するスタイル。
現場もわかる、経営もわかる——その両面の視点で、再現性のある仕組みづくりと長期的な成長を支援します。